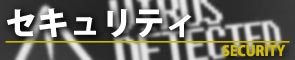サーババックアップについて現役社内SEが考えぬいた最適手段とは
さまざまなバックアップ方法やリストア時のトラブルを経験し、いろいろ調べまくって考えた結果、ベストなサーバのバックアップ方法は遠隔地レプリケーションです。
以下その理由や各種バックアップ方法の特徴、おおまかな費用についてまとめました。
数あるバックアップ方法を整理
まずはそれぞれのサーババックアップ方法についての特徴をまとめてみましょう。
比較するサーババックアップ方法について
| テープ | LTO,DAT,AITなどバックアップ用テープを利用したサーババックアップ |
|---|---|
| テープ + 外部保管 | バックアップ用テープを定期的に会社外の場所(金庫業者や社内の別拠点など)に保管するサーババックアップ |
| ディスク | テープの代わりにハードディスクを使用するサーババックアップ |
| 遠隔地レプリケーション | ハードディスク(サーバー)を遠隔地に設置し、ネットワーク経由で同期させるサーババックアップ |
さらに細かく分類すると様々なバックアップ方法がありますが、概ね上記の方法を組み合わせてバックアップとリストアの時間短縮を図るというサーババックアップとなります。
サーババックアップ方法の比較
では上記それぞれのサーババックアップ方法について特徴をまとめてみましょう。
| テープ | テープ + 外部保管 | ディスク | 遠隔地レプリケーション (複製) |
|
|---|---|---|---|---|
| 媒体の故障 | × | × | △ | ○ |
| 世代管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 建物倒壊時の復旧可否 | × | ○ | × | ○ |
| 復旧にかかる時間 | × | × | △ | ○ |
| コスト(導入費用+ランニングコスト) | △ | △ | ○ | × |
| 運用コスト(日々の手間) | × | × | ○ | ○ |
| 復元性 | △ | △ | △ | ○ |
テープによるサーババックアップをオススメしない理由
テープという切り離された媒体に保存できるということは、外部へ保管することが容易です。さらに、ハードディスクと違ってテープ自体が故障するという可能性は極めて低いのでこの点でも大きなメリットがあります。
また、テープ単位で世代管理ができるので、「1週間前の状態に戻したい」とか「1年前の状態を復元したい」という時にも便利です。しかし、実運用上、そんなケースがあるのかは疑問ですね。
かつてはサーババックアップの主流だったこのテープバックアップですが、今後はあまりオススメできません。その理由をまとめました。
日々の運用が大変
シングルのテープドライブだと、毎日のテープの入れ替え作業が発生します。
出社して、バックアップが正常に終わっているかログの確認をして、テープを入れ替えて、テープに日付を記入して、ドライで定温の保管場所に移動させる。数分で終わるこの作業も毎日となってくると作業コストは大きくなります。
土日や連休に入るとテープ交換はできませんので、休日出勤した社員の変更データについては翌月曜の夜までバックアップは取られないことになります。
オートローダー(複数のテープを自動で交換してくれるテープ装置)を導入していたとしても、結局週1回程度はマガジンごと引きぬいてテープを交換する必要があります。
「テープ交換」という地味なルーチンワークは社内SEの面白くない仕事No1と言ってもいいかもしれません。
あらゆるケースで起こりうるバックアップ失敗
バックアップソフト、OS、テープ装置、テープカートリッジ(LTO・AITなど)と必要になるものが全て違うベンダー製になることが多く、ハードやソフトの相性の問題が複雑です。そのため様々な理由でバックアップが失敗する可能性があるのです。相性とは無関係にドライブのヘッドの汚れによる書き込み失敗は日常的に起こります。
特にバックアップソフトの操作は、にわか社内SEの人には分かりにくく非常に敷居の高いものになってしまいます。
復元する自信がない
実際にバックアップしたテープから完全にデータやシステムを復旧できるかというと・・・・。
システム復元のテストは導入時にやる場合があるくらいで、その後は大掛かりなテスト環境がない限り復元テストをすることはできません。
長い運用の中で担当者が変わり、復元方法なんて分からない社内SEが担当することも多いです。いざ復元が必要になった時のことを考えず、ひたすらテープバックアップ運用を続けている会社は少なくないと思います。
フルバックアップの運用が破綻する日が来る
重複排除やデータ圧縮・ファイバーチャネルによる通信の高速化を図り、大容量のデータをできる限り短い時間でバックアップする仕組みが登場していますが、業務で扱うデータの大容量化にも拍車がかかり、イタチごっこ状態です。
テープという媒体の性質上、書き込み速度にも限界があり、週に1回行うフルバックアップが翌営業日まで終わらないなんていう日が来ないとも限りません。
何かとテープに残したくなってしまう
例えば、ファイルサーバーの空き容量が少なくなってきたから、5年以上前のデータをテープにバックアップしてサーバー上からは消してしまおう、と考えたとしましょう。
それから5年経って、「10年前の顧客資料があったはず!」ってことでそのテープを引っ張り出してきても。あれ?この時のテープに対応するテープ装置が無い。。。
残したテープはいつでも読み出せるようにそのテープ装置、ソフト、ソフトが動作するOSをずーっと残して行かなければいけないのです。
このあたりは会社によって考え方があると思いますが、「必要になるかもしれないから保管」が生み出す運用コストは結構なものなんです。
保管が必要な物を明確にしておくことはサーババックアップを効率化する上で非常に大切なポイントです。
遠隔地レプリケーションについて整理
そもそも遠隔地レプリケーションとはというところを説明しておきます。
本社にあるサーババックアップを遠隔地にあるデータセンターに取る場合を想定しましょう。まず、本社とデータセンターに同じ構成の機器を設置し、レプリケーション設定をしておきます。本社とデータセンターはお互いに通信出来る状態とします。
本社サーバーのデータに変更が加わると、ネットワーク経由でリアルタイムにデータセンター側のサーバーデータも変更されます。
ネットワーク負荷が心配な場合はリアルタイムではなく、夜間にスケジューリングすることもできますし、通信自体は変更したファイル分のデータではなく、そのファイルの中でも変更された部分だけのブロックデータを送信しますので、かなり小さな容量のデータ通信となります。
これにより、本社サーバーの故障、停電、もしくは本社ビルの倒壊があった場合、データセンター側のサーバーをメインとして切り替えることでユーザーはそれまでと全く同じ環境にアクセス可能となります。
遠隔地レプリケーションをオススメする理由
サーババックアップについて最も重要視しなければいけないのは、「確実に復元できること」です。テープにバックアップしてるから大丈夫と、理論上のデータの存在に安心感を抱きつつ、いざ戻せと言われた時にちゃんと戻せるのか不安に感じている社内SEの人たちは意外に多いです。
そこでオススメしたいのが遠隔地レプリケーションによるサーババックアップです。
運用が楽
テープ交換もなく、せいぜいレプリケーション状況のログ確認をする程度です。
確実に復元できる(すでに復元されている)
本社側が壊れたらデータセンターをメインにする切り替え作業だけです。
優れたスナップショット機能で世代管理もOK
常にサーババックアップは最新の状態になってしまいますが、スナップショット機能を併用することで世代管理が可能となり、1週間前、1ヶ月前の状態に戻すこともできます。
ダウンタイムの大幅短縮
大容量データをバックアップソフトから読み出す必要はないので、実質ダウンタイムは切り替え作業時間だけ。
大容量のバックアップも時間を気にせず可能
変更されたデータをその都度、ネットワーク経由で流してしまうので、バックアップ時間を気にする必要はありません。
高度なスキルや知識は不要
使う機器もソフトも理解しやすいものばかりなので、復元作業についても高度なスキルを要求されません。例えあなたが高度なスキルのある社内SEだとしても、後任の社内SEや、緊急時には別の担当者でも対応できるシンプルな手順でシステムを準備することは、事業継続において経営者側が重要視するポイントでもあります。
一つのベンダー内で完結する
ストレージとバックアップの仕組みが一体になっているハードウェアを購入するため、ほかのハードウェアとの相性や互換性を気にする必要がありません。
決して高くないレプリケーションによるサーババックアップの費用
テープバックアップとレプリケーションによるサーババックアップでどの程度費用に差が出るのか比較してみました。
■テープバックアップ
もっともシンプルなテープバックアップの構成です。
| 品名 | 参考製品 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| サーバー | HP ProLiant DL320 G6 | 400,000円 |
1 |
400,000円 |
| テープ装置 | HP 1/8 G2 LTO テープオートローダー |
500,000円 |
1 |
500,000円 |
| テープ | LTO4 Ultrium | 13,000円 |
20本 |
260,000円 |
| バックアップソフト | CA ARCserve Replication | 100,000円 |
1 |
100,000円 |
| テープの外部保管費用 | 一般的な倉庫事業社の価格 (月額) |
5,000円 |
12か月 |
60,000円 |
| 年間人件費 | 時給1200円のSEが 1日10分要した場合 |
200円/1日 |
245日 |
49,000円 |
テープによるサーババックアップ費用 合計 1,369,000円
■レプリケーションによるバックアップ
すでに存在する支店を利用してレプリケーション先サーバーを設置できた場合の費用です。
| 品名 | 参考製品 | 単価 | 数量 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| サーバー | HP ProLiant DL320 G6 | 400,000円 |
2 |
800,000円 |
| バックアップソフト | CA ARCserve Replication | 100,000円 |
1 |
100,000円 |
レプリケーションによるサーババックアップ費用 合計 900,000円
シンプルなラックマウントサーバー1台で構成したパターンで見積もってみると、テープバックアップよりも安くなっていることが分かります。
上記のパターンは差が無くなるように条件を揃えたものですが、複数の拠点を持ち、現状もサーバーが支店に分散している環境であれば、既存の環境をうまく利用することで当てはめられるシミュレーションとなります。
もちろん機器の構成次第で大きな差が生じることもありますが規模が大きくなればなるほどレプリケーションバックアップのメリットは大きくなることは間違いありません。
次は→ DNSサーバーのベストな運用とは?DNSは社内で独自に立てるべき?
 |
DNSサーバーのベストな運用とは?DNSは社内で独自に立てるべき? |
 |
Windowsファイルサーバーの最適な運用ルールとフォルダ構成とは? |
 |
高速コピーツール「FastCopy」はホントに早かった!ファイルサーバー移行テスト |
 |
ActiveDirectoryとは|できることを噛み砕いて説明 |
 |
社内にあるサーバー種類とその管理方法について |
 |
別のプログラムがこのフォルダーまたはファイルを開いているので・・・の原因と解決方法(2015/11/24) |
 |
ファイルサーバーのアクセス権を一括確認(2014/02/14) |
 |
テレビ会議システムとWeb会議システムはどっちを選べばいい?(2014/02/06) |
 |
Web会議システム「V-CUBE」と「Meeting Plaza」徹底比較(2014/02/06) |
 |
現役社内SEが考えたWeb会議システムの選び方(2014/02/06) |
 |
iPhoneからリモートデスクトップできるアプリ「LogMeIn」(2014/01/22) |
 |
EMC「VNXe3100」の重複排除でファイルサーバーを超効率的に運用する(2014/01/16) |

- 1976年 東京都生まれ
- 23歳・・・サービス業の会社に勤務したが時間的自由度の低さに納得行かず転職を考える。
- 25歳・・・「新卒扱いで構いません!」と言ってIT系企業(社員30名)に転職。
Word、Excelから始め、サーバーやネットワーク機器の構築を学び、3年間SIerとしてお客様への提案やシステム構築を行う。 - 28歳・・・「3年の経験あり」ということで現在の会社(従業員数900名)に社内SEとして入社
遅れに遅れていた社内システムを低予算で更新した実績を評価された。